-150x150.webp) りさ
りさ家庭菜園の残渣を捨てずに活用する方法に堆肥化があるわね。



以前にも紹介したけど、もっと良い方法に改良したので紹介します!
今回紹介するのは、『【生ゴミが減る!】家庭菜園の残渣や生ごみはキエーロで堆肥に!』で紹介した残渣の堆肥化の改良版。


以前の方法のデメリットとして以下のものがありました。
- 袋栽培の土を利用するので、大量の残渣を処理できない
- 土に還元するにも袋栽培の土の量は少量のため、大量の土に対応できない
このデメリットを解決する方法が、今回紹介する方法です。
本記事の方法を利用することで
- 100Lを超える量の土を使って残渣を堆肥化できる
- 堆肥化するスピードを上げ、窒素飢餓を起こしにくい
- 微量栄養素の補給もできる
ということができます。
よかったら最後までご覧くださいね。
- ボックスを使うと大量の野菜くずや、残渣を処理できる
- 早く分解させるには米ぬかと硫安、鶏ふんを入れること
- 微量栄養素補給には有機石灰を投入する
- 2021年からベランダで家庭菜園を開始!
- ミニトマトを約120個、きゅうりを約60本以上収穫!
- これまでに10種類以上の野菜を栽培した経験あり
動画で本記事の内容を確認


本記事の内容を動画にてまとめています。
ミニトマトの残差を使って1度使用した土を再利用させる方法を分かりやすく紹介しているのでよかったらご覧下さいね。
野菜くずや、残渣を簡単に堆肥化する方法とは


この記事では、『【プランター菜園】使用済みの土の保存・管理方法について』で紹介したボックスを流用しています。


このようにすることで、簡単に大量の野菜くずや、残渣を土の栄養に変えることができます。
その理由は以下の通りです。
- 家庭菜園をしている方は土がどんどん増える
- 土を1箇所にまとめて保管した方が管理が楽
- 蓋を閉めれば上に乗ることもできるので、ちょっとした椅子にもなる
家庭菜園をしていると、色んな野菜や草花を育てたくなります。
培養土が足りなければ追加で購入しますが、使い終わった土が新たに増え、保管場所が悩みのタネに。
-150x150.webp)
-150x150.webp)
-150x150.webp)
色んな野菜を育てたいから培養土買ったけど、一体どうしたら…
そういうときに、大きめのボックスがあればある程度土の量が増えても問題ありません。
大は小を兼ねると言いますが、あらに購入した培養土の保管場所に困らないのは思いの外ストレスがありません。



大きなボックスを使えば土の保管場所になるし、土を再生させることもできるから一石二鳥!
野菜くずや、残渣等を早く分解するには?


野菜くずや、残渣等を早く分解するには以下のものがあると便利です。
それぞれについて詳しく紹介しますね。
※以下の項目をクリックすると移動します。
※以下の項目をタップすると移動します。
米ぬか
米ぬかは微生物のエサになります。
米ぬかにも栄養があり、窒素・リン酸・カリだけでなく、ミネラルも含まれているため肥料として申し分ありません。
| 窒素 | リン酸 | カリ | カルシウム | マグネシウム |
| 1.18% | 2.1% | 1.3% | 0.012% | 0.7% |
米ぬかにはリン酸が多く含まれているので、実を収穫するミニトマトやきゅうりなどの野菜にはピッタリな栄養素と言えます。
他にも花を咲かせる草花にも効果的なので、どの植物にもメリットがあります。
-150x150.webp)
-150x150.webp)
-150x150.webp)
米ぬかは工夫次第で無料で手に入るな。
微生物が活発になれば土が豊かになるし、コスパが良いな!
硫安、または鶏ふん
米ぬかを入れると微生物が増加し、野菜くずや、残渣を分解する速度が速くなります。
このとき、微生物が分解する際に必要な栄養素に窒素があります。
微生物が窒素を大量に消費して分解してくれるので、一時的に土の中に含まれる窒素が足りなくなることがあります。
これが窒素飢餓です。
窒素が足りなくなると分解速度が遅くなるだけでなく、その土を使って何かの植物を育てようと思っても最初から窒素が足りない状態からスタートします。
そのため、茎や葉の生長が遅いだけでなく、光合成も通常よりできないので病気に虫の被害にあった際に枯れやすくなります。



折角土を再生させても植物が育ちにくいなら意味がないよ!
そうならないためのポイントとして、米ぬかを入れたときに一緒に窒素を多く含む肥料を入れるのが効果的です。
鶏ふんも同様に安価に手に入り、窒素を多く含みます。
ただ、鶏ふんには独特の匂いがありますが、以下で紹介している鶏ふんはほとんど臭いのしない炭化鶏ふんです。
ベランダ等で家庭菜園をしている方にはピッタリだと思います^^
有機石灰、または苦土石灰
先に紹介した米ぬかや、硫安または鶏ふんで植物の3大栄養素(窒素・リン酸・カリ)を補給することができます。
しかし、植物の生長にはマンガン、鉄、銅などの微量栄養素が不可欠です。
有機石灰がなければ、苦土石灰をいれてマグネシウム・カルシウムの補給を狙います。
有機石灰・苦土石灰については、『有機石灰の使い方!土の再利用でコスパの良いプランター栽培』で詳しく紹介しています。


こちらの記事では、石灰を利用することのメリット・デメリットを解説するだけでなく、補給できる微量栄養素とはどんな効果があるのかも紹介しています。
たくさんはいらないけど、無ければ植物が上手く育たない。
そんな微量栄養素が意外とたくさん種類があります。
そういったものを簡単に補給できるのは『有機石灰』です。
-150x150.webp)
-150x150.webp)
-150x150.webp)
微量栄養素を補給するには有機石灰がおすすめね!
カルスNC-R
ネットの記事や、Youtubeで話題となっているカルスNC-R。
こちらについて調べてみると、かなり効果のある複合微生物資材です。
この『微生物資材』とは、微生物自体を特別な方法で生きたまま粉状に保管し、土に混ぜることで微生物自体を物理的に増やすことができます。
微生物は大きく分けて、酸素を好む微生物『好気性微生物』と酸素を嫌う微生物『嫌気性微生物』の2種類があります。
そのため、微生物の種類が多いので野菜くずや、残渣等と一緒にカルスNC-Rをすき込むことで分解時に発生するガスを発生させずに堆肥化できます。
通常なら未熟な堆肥があると有毒ガスによって植物の根を痛めて枯れることがあります。
一方でカルスNC-Rを使うと堆肥化していない野菜くずや、残渣を土の中にあっても育てる植物に影響が出ません。
-150x150.webp)
-150x150.webp)
-150x150.webp)
カルスNC-Rを使うと完全に堆肥化していなくても、育てる植物に影響が出ないのね。
そして、土の中の微生物の種類が増えると以下のようなメリットがあります。
- 連作障害対策になる
- 連作障害は微生物の単純化が原因と言われている
- 土の中の微生物の種類を増やすことで連作障害の起きにくい土にする
- 土の中に良い菌を増やして悪い菌の影響を減らす
- 病気になりにくい環境を作れる
カルスNC-Rを使う際には窒素飢餓がおきて失敗することが多いようです。
窒素飢餓がおきないように硫安を利用し、籾殻を利用するのが良いようです。
まとめ:プランターの土を有効活用:コスパの良い再生土で家庭菜園を始めよう
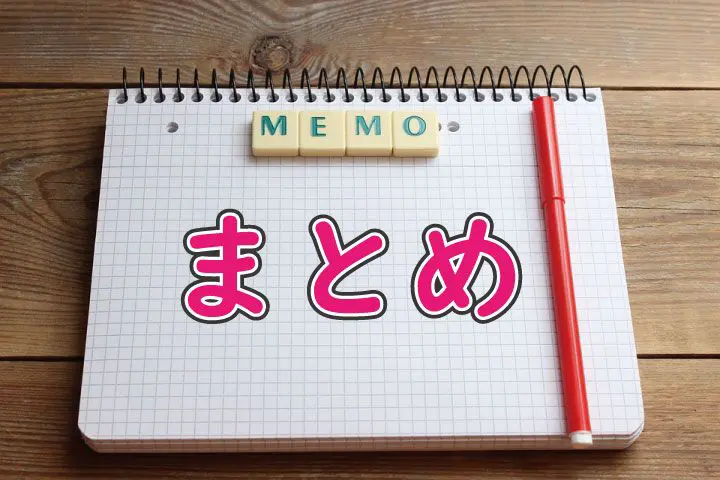
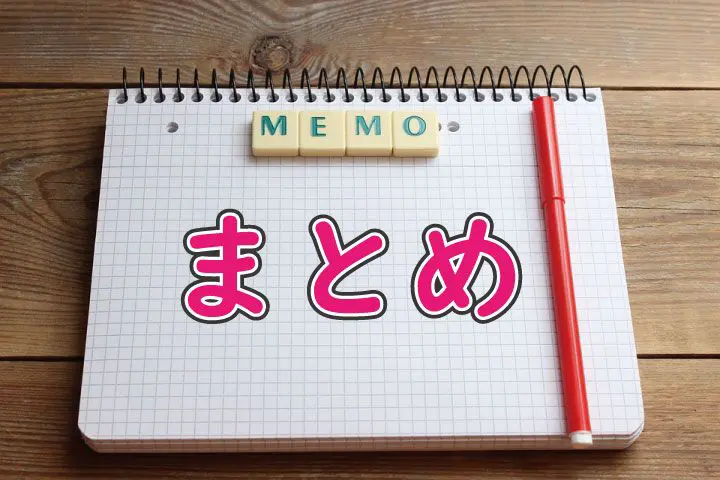
最後までご覧いただきありがとうございます。
今回の方法を使うことで
というメリットがあります。
ぜひ誰でもできる方法だと思いますので、チャレンジしてもらえたら嬉しいです^^
LifeNagiブログでは家庭菜園の記事を他にも投稿していますので、ぜひ他の記事も見ていただければ嬉しいです。
再生した土は本当に使えるの?という疑問を実際に使って栽培した様子を紹介しています。


大量に土がないからボックスを使う必要はないけど、土を再生させてコスパよく楽しみたい!
そんなときはこちらの記事がおすすめです。


それでは、なぎ(@lifenagi)でした。

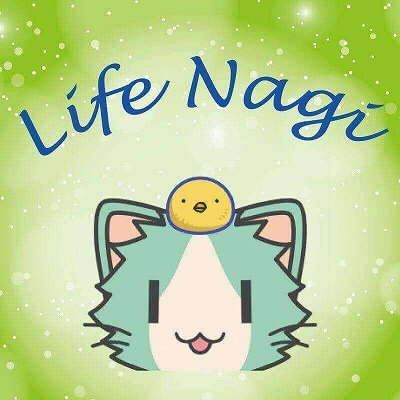








コメント